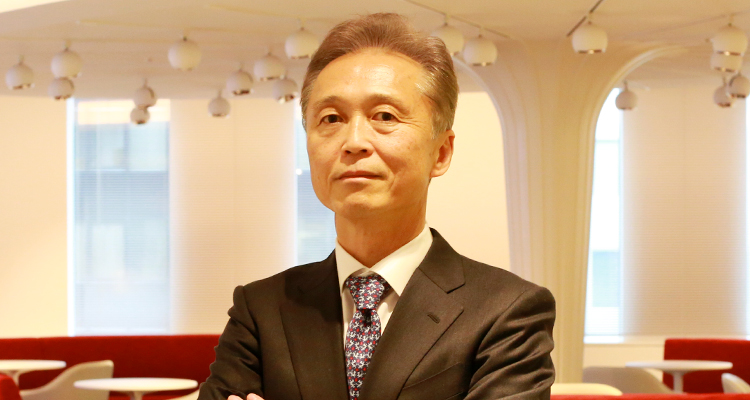- 安川健司
- 1960年生まれ。東京大学大学院農学系研究科修了後、同社に入社。入社4年目から前立腺治療薬の開発業務に従事するため、7年間米国に渡る。そこで、当時国内にいては経験できなかった薬事規制下で真に科学に根付いた薬剤開発業務を習得し、帰国後は開発本部でプロジェクト推進グループ部長や執行役員製品戦略部長、代表取締役副社長などを経て2018年に代表取締役社長兼CEOに就任。
- https://www.astellas.com/jp/
アステラス製薬は、新薬を作る会社です。一つの新薬を世の中に送り出すまでには、基礎研究と臨床開発を合わせ9年から17年と大変長い年月が費やされます。しかし、新薬の特許期間は基本的に20年。ジェネリック医薬品の利用が政府主導で推進されているなか、いかに継続的に新薬を作れるかが経営の肝です。治せない病気はまだまだ多くあるので、新薬により患者さんの治療選択肢を増やすことが、我々の社会的使命です。科学の進歩により人間の寿命が伸びていますが、相反して地球環境が悪化しているという事実にも目を向けなければいけません。サステイナブルな地球を守るという心を忘れずに事業に取り組んでいきたいと思っています。
アステラスの新薬を海外へ羽ばたかせるために。

東京大学大学院時代の専門領域は天然物化学でした。海綿や、サンゴ、イソギンチャクなど海洋の無脊椎動物の中から、新薬につながるような未知の化合物を採取し研究を行っていました。酸素ボンベを担いで海に潜り、見たことのないような生物を捕まえ、新しい作用を起こす成分を見つけると「これが世の中に役立つのかもしれない」とワクワク感を募らせていました。当時、山之内製薬の生化学研究室と共同研究をしており、開発部長から「君はきっと研究よりも臨床開発に向いている」と声をかけられたのをきっかけに、山之内製薬に入社しました。開発部門に配属され、新薬の製造販売を認めてもらうために行われる臨床試験の“イロハ”を3年間学んだ後、米国に渡ることになりました。当時の山之内製薬は、日本以外の国で薬を販売することはできておらず、海外の製薬会社にライセンス供与して販売してもらうビジネスを行っていました。そこで、より大きな成長の機会を得るべく、米国、欧州に開発拠点を持ち、自分たちで創った薬を自分たちで販売していくことを目指したのです。1980年代終盤から1990年代にかけて、日米の間には、新薬の有効性・安全性を証明する方法や能力に大きな差がありました。米国では、効果のない偽薬、あるいは比較のための治療を施した比較対照群を用いた大規模臨床試験を実施し、統計学を用いて結果を評価する手法が確立されていました。また、FDA(米国食品医薬品局)自身でも独自の解析を行い、承認の判定を行っていました。一方、日本では試験の規模自体が小さく、統計学的に信頼に足る分析ができるような試験はまれでした。当時、私は米国で新薬開発の現場を目の当たりにしてきましたので、日本の臨床試験体制の遅れに驚きを隠せませんでした。7年間開発を行い、米国、欧州諸国で製造販売承認を取得したときは、まさに感無量でした。その販売を許可する証明書のコピーを今でも大切に保管しています。
一つの新薬ができ上がることで、会社の売り上げは飛躍的に上がります。日本だけでなく、世界中で販売されることで10倍以上の価値になっていくわけです。輸入医薬品に頼っていた日本が、輸出もできるようになっていくという進化に、少しでも貢献できたことは誇りに思っています。「海外で販売できる薬を作る」という大きなミッションに成功した私は、開発のリーダーを任されることになります。その時、当時の社長に呼び出されて言われたことは「これからは、習うのではなく、どうやって競争相手よりも早くやるかだ。とにかくスピードにこだわれ」ということでした。
新しい挑戦が、会社の進化を作る。
スピードを上げようとすると、一つのタスクにかける時間を短縮する必要がありました。これまでは、一つの結果を見て、次のステップへと進んでいました。それを、失敗のリスクを承知の上で、複数のタスクを同時に進めていく、というマインドセットをメンバー全員に持たせることは非常に大変なことでした。また、プロジェクトリーダーともなると、関連部署も多くなり、自分より目上の社員をコーディネートしていかなければならないことも大変でした。小さな成功を積み重ねていかなければ、人を動かすことはできないとも痛感した時期でした。
2005年に、山之内製薬と藤沢薬品工業が合併してアステラス製薬へと生まれ変わったことを機に、進化のスピードはますます上がっていきました。まずはいろいろな基準が異なる2社が1社になるわけですから、新しい基準を作ることが求められ、どちらかを優先するのではなく、どちらにも偏らない新しい会社を作ろうというプロジェクトを進めたことは思い出深い経験です。
製品戦略部の部長を務めた際には、当時のビジネスモデルの変革を訴えました。売り上げの半分を占めていた、主力商品とも言える新薬の特許が切れるタイミングで、従来の医薬品の有効成分と同一の効能・効果でありながら、化学構造が異なっている薬(改良型医薬品)の開発に取り組んでいたのですが、それだけのことでは、その後必ず安く購入できるジェネリック薬品に取って変わられてしまいます。同じ分野に固執するのではなく、新しい科学を追い求め、その時は治療満足度の低い病気であっても、5年後、10年後を見据えて画期的な新薬を作っていくことこそ大事であるという風土を、地道に作り上げていきました。
その後、経営戦略担当役員を務め、それまでの内作志向を断ち、大学や企業との連携を積極的に進めることで、科学の進歩をいかに早く取り入れるか、ということを重視するようにしました。研究開発の現場に新しい波が起こることで、その波は広がりを見せ、細胞医療や遺伝子治療にまで分野を広げることになりました。経営に新たな風を取り入れようとすれば、長く続いてきた会社ほど社内からの反発が当然のように起こります。最初から大人数の同意を得られなくても、少人数で一歩ずつ始め、成功体験を積んでいけば段々と賛同する人数が増え、組織改革へとつながっていきます。今後、科学やテクノロジーが進化すれば、病気を治すというだけではビジネスとして成り立たない時代がやってくるかもしれません。新しいことを恐れず、スピード感を持ちながらも小さな努力を継続し、常にビジネスの幅は広げていきたいと思っています。
Loading...