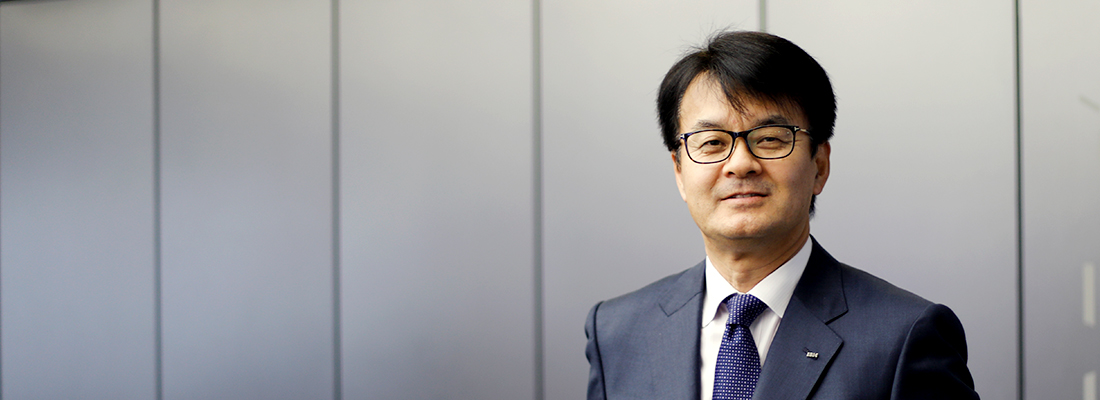- 山口明夫
- 1964年生まれ、和歌山県出身。87年、日本IBM入社。エンジニアとしてシステム開発・保守に携わった後、2000年問題対策のアジア太平洋地域担当、社長室・経営企画、ソフトウエア製品のテクニカルセールス本部長、米国IBMでの役員補佐を歴任。理事、執行役員、常務を歴任し、取締役専務執行役員、グローバル・ビジネス・サービス事業本部長を経て19年5月から現職。本社経営執行委員も務める。
- https://www.ibm.com/jp-ja
社長に就任して2年目ですが、人間的に今までと変わったわけでもなく、社長という役割をこなしているに過ぎません。今まで様々な部署で経験を積む中で、国内外、社内外問わず、誰とでも分け隔てなく付き合いオープンに会話し、信頼関係を築いていくことの楽しさを何よりも学んだので、これからもそのスタンスは大切にしたいですね。「外資系企業にしては人に優しすぎる」と評されることもありますが、悪いことではないと思います。一人ひとりの存在意義を認め合える会社でありたいですね。
会社の第一印象は「自分には縁がなさそう」

和歌山の田舎で果物農家の長男として生まれ、両親の働く姿を見ながら育ちました。いずれ自分が継ぐのだろうなと漠然と考えていました。
大阪の大学に進学し、工学部で学びました。卒業後は実家へ帰るつもりで地元の企業の就職面接を受ける準備をしながらも、都会でITの仕事をしてみたい気持ちもありました。そんな時、教授からIBMを受けてみたらどうかと勧められたんです。いろんなIT企業が台頭していた時代で、IBMは急成長中で待遇も良く人気がありましたが、それ以上にハードなイメージでした。なんとなく自分には縁のなさそうな会社だなと思いながらも面接を受けてみたら、あっさり内定をもらいました。入社してみると、同期は堂々と歯切れよく話す人ばかりで、自分には場違いじゃないかと悩みました。それでも物理やITの分野は好きだったので、仕事は楽しみでもありましたね。
最初の2年はソフトウエアのコールセンターに配属され、障害対応を担当しました。応対用のマニュアルがあったとはいえ、大した知識もない新人によく務まったなと今考えても恥ずかしい気持ちになります。きっと陰でベテランの先輩方がフォローしてくれていたのだと思います。
3年目に大阪から東京に異動し、銀行の現場に配属されました。周りは精鋭ばかりで、経験の浅い私は度々足を引っ張っていました。あるプロジェクトのメンバーに選ばれた時のこと、周囲は「彼では無理ではないか」と上司に進言したようでした。しかし上司は「彼は諦めずに頑張るし必ず役に立つようになるから、ここに置いてやってくれ」とみんなを説得して回ってくださったそうです。ずいぶん後になってそのことを知りました。新人の私を懸命に育てようとしてくださった上司に心から感謝していますし、上司の「部下を信じて育てる」姿勢は、今の私が大切にしていることでもあります。新人でも、信頼されていることを実感するとやりがいを感じて頑張れるものです。
後に難しいプロジェクトの責任者を任され精神的に参っていた時も、私を自宅に招き、とことん話を聞いて激励してくださった上司がいました。周囲の人には本当に恵まれていたと思います。今の私があるのは根気強く成長を見守ってくださった上司やお客様、部下たちのおかげです。
エンジニア出身の社長就任は初めて
海外で仕事をする機会も多かったのですが、欧米企業の役員は経営の数字や状況がすべて頭の中に入っているんですね。経営会議の場で資料を見なくても、過去の売り上げ、エリアごとの利益率、その改善のために必要なアクションなどを把握しています。これが外資系企業なんだなと実感します。私も最初は感心するばかりでしたが、欧米の非英語圏のメンバーに「ノンネイティブが英語で議論をしても英語圏の人たちには絶対に勝てないから、数字だけは頭に入れておいたほうがいい」と助言され、そのスキルを必死に習得しました。確かに、数字が誤解を招くことはないし、数字から入ることで本質的な議論ができます。
そして昨年、前任の社長が米国に帰任するのを機に、私が後任に指名されました。歴代の社長は営業経験者ばかり。エンジニア一筋でやってきた自分に務まるか不安でしたが、同時に今まで問題を感じていた部分を改革できるチャンスだと思いました。
一番変えたかったのは、どの事業部でも自分が担当する仕事にしか目を配れないところでした。社員たちにそのつもりはなくても、査定や評価の軸が「この製品をどれだけ売ったか」というような限定的なところにあったので、当然だったと思います。まずそこを変えて、社員みんながお客様のために一丸となって取り組める環境を作ることを心掛けました。今後は社員たちがもっと働く楽しさを感じられる仕組みや風土を充実させていきたいですね。お客様や社員にとって何が大事であるかを常に考え抜いている会社でありたいです。
何が起こるかわからない時代です。嘆くのではなく、一つひとつの変化を前向きに受け止めて、どのように生かして新しい世界を作っていくか考えたほうがいいと思います。自分の考えを積極的に発信し、実践していくことが大切です。一緒に頑張りましょう。
Loading...