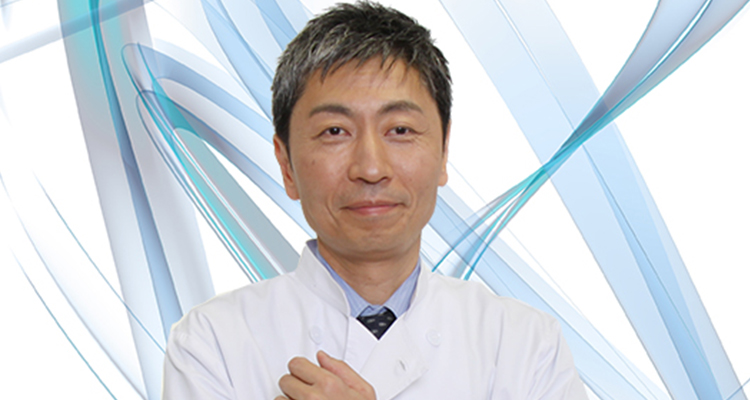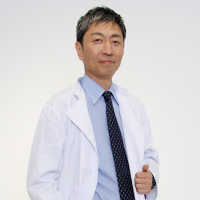- 杉浦敏之
- 1963年生まれ、埼玉県出身。千葉大学医学部卒業、医学博士。大学卒業後、2年間千葉県救急医療センターに勤務。その後13年間外科医としてさいたま赤十字病院などに勤務し、2003年に開業。在宅医療に注力し、06年に県南在宅医療研究会を設立。埼玉県立大学非常勤講師、上尾中央看護専門学校非常勤講師、日本尊厳死協会関東甲信越支部理事、川口市医師会理事、日本在宅医療連合学会、指導医、評議員。
- https://koukeikaisugiuraiin.jimdo.com/
医療の現場で仕事をしていると、度々厳しい状況に直面します。病院で患者様の容体が急変すれば、医療者もご家族も当然険しい表情になります。ところが、在宅診療を始めて気づいたのですが、自宅だと患者様が辛い場面や亡くなって悲しい場面であっても、和んだりふと笑顔になれる瞬間があったりするものなんです。これが自然な死なのかもしれませんね。厳しい局面でこそ、ユーモアや笑顔が持つ力の大きさを実感します。
退院したくてもできない患者様のために

父が開業医で、自宅の1階が診療所だったんです。幼い頃から父の仕事を間近で見て、かっこいいなと憧れていました。小6の時の文集には「医師になりたい」と書いていましたね。医学部を出ると、救急をやりたくて救急医療センターに飛び込みました。エキサイティングなところに引かれたんですよね。生死をさまよう人を助けるわけですから。救急で2年働き、心臓外科や消化器外科の経験も一通り積むと、大学院で勉強して総合病院に就職しました。ここでは、主治医としてかかわった患者様とは最期までお付き合いをするものなのだということを学びました。患者様と正面から向き合わないといけない。逃げてはいけない。それが医師としての覚悟なのだと知りました。
患者様の中には、病状が思わしくなく入院が長引いてしまう方もいらっしゃいます。皆さん、本当は残された貴重な時間を住み慣れた自宅で過ごしたいと思っているんです。しかし、そのような方は抗がん剤の治療中だったり点滴が必要だったりするので、病院を離れるわけにはいかないのです。何とか患者様の希望に沿う手立てはないものかと悩んでいたところ、自宅での医療行為を引き受けてくださる地域の開業医の方が僅かながらいることを知りました。在宅医療のことを真剣に考え始めたのはその頃からですね。 ちょうど同じ頃に、高齢の父に診療所を手伝ってほしいと打診されたのがきっかけで、独立して在宅医療に本格的に取り組む決心をしました。私が病院を退職するのと同時に、末期の食道がんの患者様がご本人の希望で退院したんです。ご自宅が父の診療所から近かったこともあり、翌日から毎日点滴を持って患者様の元へ通うことで訪問診療が始動しました。
最初は私ひとりで奔走していましたが、地域の訪問看護ステーションの方々の協力を得て、24時間体制のサポートが実現したのです。在宅医療で一番重要なのは患者様を不安にさせないことですから、地域の医療機関との連携は欠かせません。また在宅医療はご家族の心身にも大きな負担が掛かりますから、ご家族にも安心していただかなくてはいけません。
患者様やご家族から学ぶ日々
勤務医の時は、患者様やご家族と話す時間がないことが一番のストレスでした。訪問診療は患者様やご家族とリラックスして話をすることができ、治療に役立つ情報も引き出しやすいんです。段差やトイレまでの距離など住環境も治療方針に大きくかかわります。診療所に来られた患者様に対しても、ご自宅での様子を想像しながら診療するようになりました。
技術的なことは若い時にたくさん学びましたが、今は患者様やご家族から学ぶことがとても多いです。時には、「私はいつ死ぬんですか」などと、答えに窮するようなことを聞かれることもあります。はぐらかすことはいくらでもできますが、それでは患者様は取り残されてしまいますよね。そのとき、どう考えるかが勝負。「これが正解」というのはないんです。 私は常に「自分はどうしたいか」を考えるようにしています。たとえば私なら、笑って死にたいと思っています。でも死生観は人それぞれ。好きなことをやり遂げたい人もいれば、一日でも長く生きるために闘病を頑張る人もいるでしょう。医療者は患者様の希望を聞き、最善の道を選べるように様々な選択肢を用意することが大切だと思います。
これからもさらに在宅医療の輪を広げていきたいですね。医療従事者をはじめ、自治体や国民に対しても啓発をしていきたいと思います。若者の皆さんには、いろんなことに好奇心を持って取り組んでほしいですね。趣味をたくさん持つのもいいと思います。多くの学びが得られるはずです。医療に携わる方は、新しい技術の勉強を怠ることなく、日々知識のアップデートをしてください。そして、患者様やご家族と向き合うことを忘れないでください。
Loading...