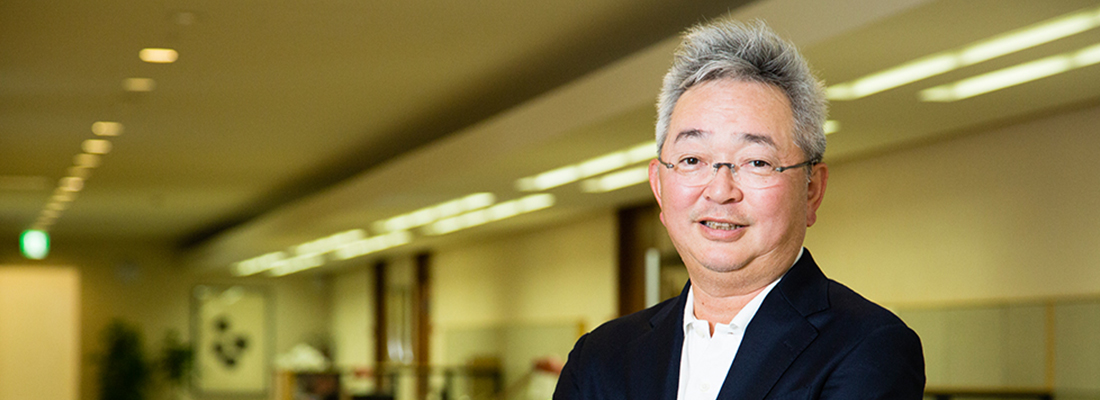- 盛田昌夫
- 1954年生まれ、東京都出身。ソニー創業者の盛田昭夫氏の次男として生まれる。ジョージタウン大学卒業後、モルガン銀行を経て、81年ソニーに入社。ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役社長、ソニー業務執行役員常務を歴任。2009年、ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役会長に就任。
- https://www.sonymusic.co.jp/
父がソニーの創業者でした。当時はまだ小さな町工場のような雰囲気でしたね。仕事を終えた父が社員たちを引き連れて帰宅し、我が家の食卓をにぎやかに囲んでいたのを覚えています。みんなチャレンジ精神旺盛で、キラキラと輝いて見えたものです。幼い頃からそんな大人たちの姿を見て育ったためか、私自身も新しいことに挑むときに「できない」と立ち止まるのではなく、「どうしたらできるか」と考えるようになりました。
ハードとソフトの融合

私がソニーに入社したのは1981年。オーディオ事業部に配属されたのですが、ちょうどその頃オーディオ業界は大不況で、すっかり行き詰まっていました。そして、時代はアナログからデジタルへの過渡期を迎えていました。レコードに代わってCDが世に出回るタイミングでもあったんですね。新しい商品が次々に出てくるし、コピーや著作権管理など、アナログの時代にはできなかったことができるようになりました。そこにハードウエアの側面から携わることができたのは幸運だったし、面白かったですよ。新しい価値観、規格や分配などのルールを作り上げていくことに非常にやりがいを感じました。
90年代を前にソニーは米国大手のCBSレコードを買収し、「ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)」が誕生しました。ハードウエアの会社がソフトウエアの会社を買ったわけです。私は98年にSMEの理事に就任したのですが、ハード出身のトップマネージャーなんて初めてでしたから、みんな「畑違いの人にソフトの事情が分かるのだろうか」と思ったでしょうね。厄介なことになったと思ったはずです。でも、ハードとソフトは車の両輪のようなもので、双方が足並みをそろえて変化していかなくてはならないと私たちは考えていました。
90年代以降の音楽業界はCDレンタルやカラオケブーム、MDの登場などで一層目まぐるしく変化していきました。ハードとソフトのバランス感覚が重要な時代になったと痛感しましたね。
ドキドキする会社であってほしい
インターネットの普及とともにCDから音楽配信へとかじを切ることを決心した時は、あらゆるレコード会社を訪ね歩いて「きちんとリスナーにお金を払ってもらう仕組みにします。音楽は著作物ですから」と説明して回りました。この取り組みによって、日本では「音楽は買うもの」という概念が世界中のどの国よりも定着したと思います。そのきっかけを私が作ったんだという自負がありますよ。
私の人生からソニーを切り離して考えることはできません。子供の頃から「SONY」の4文字に慣れ親しんで育ったし、人生の大半はソニーと共に成長してきましたからね。ソニーはドキドキするような会社じゃないと駄目だと思うんです。今までソニーでハードもソフトも手掛けてきましたが、どんなときも「次はどんなドキドキすることをしようか」と社員たちと考えながら歩んできました。今のソニーはそうじゃなくなってしまった部分もあって少し残念ですが、これからの世代がまたソニーをドキドキする会社にしていってくれると期待しています。
人よりも先にチャレンジすれば、人よりも先に失敗します。でも、人よりも先に「2回目」に挑戦できるということでもあるんですよね。考えるよりも先に行動を起こすことが大切です。まず体を動かしてみる、ということを忘れずに、いろんなことにチャレンジしてほしいと思います。
Loading...