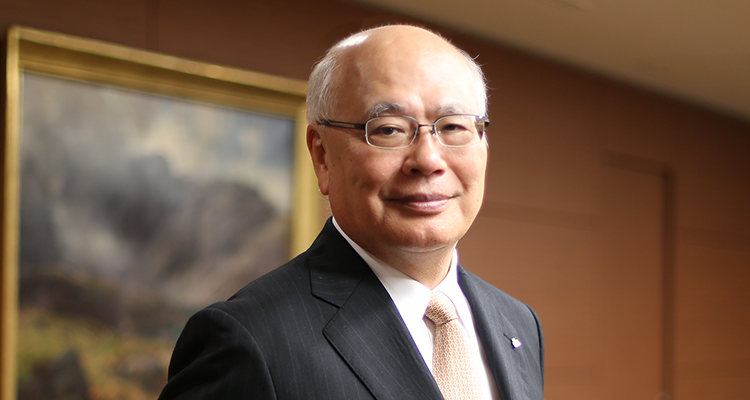- 宮原道夫
- 1951年生まれ、東京都出身。75年に早稲田大学大学院理工学研究科修了後、森永乳業に入社。技術職をメインに経験を積み、2005年に常務執行役員、12年に代表取締役社長に就任する。社内では「良いモノをつくれば勝手に売れた」という時代の価値観を払拭しつつ、「技術の森永」の長所を今後の100年にわたり確立すべく、経営革新を推し進めている。
- http://www.morinagamilk.co.jp
商品をつくる側がどんなに素晴らしいと思うものをつくっても、実際に売れるとはかぎりません。なぜならそれは、必ずしもお客さまが心から求めるものとは限らないからです。しかし当社が積み上げてきた経験や技術の中には、お客さまに求められる商品をつくり出すためのヒントがたくさん詰まっています。つまり経験や技術の蓄積こそが、当社の強みなのです。2017年に創業100周年を迎える当社は、これからも社会に役立つ企業、社会に必要とされる企業を目指しています。
厳しくも楽しかったエンジニア時代

私は団塊世代より少し後の世代になりますが、生まれ育った東京・神田には、まだ地域共同体が根付いていました。住人たちが助け合って生きるのが当たり前の社会だったんです。子どもたちは、たとえ学年が違う生徒同士であっても、みんなで仲良く遊んでいました。地域ではお祭りや盆踊り、相撲大会や町内対抗リレーなど、住民が交流する場もたくさんありました。そうした助け合いの気風が私は大好きでしたし、それが社会に出てからの自分自身に大きな影響を与えたのだと思います。
大学院修了後、人の役に立つ仕事をしてみたいという思いから、森永乳業へ入社することを決めました。また食品関連の会社であれば、広い視野で自分のアイデアを生かせるのではないかと思ったのです。当時の社会は機械化・自動化の変革がすさまじく、農業もやがては工業的になっていくだろうと思われていました。小さい頃からものづくりが好きだった私にとって、自分を生かすチャンスです。入社直後から技術職にやりがいを感じていましたし、仕事そのものが楽しくて仕方ありませんでした。
当時は何をつくるにしても、既存のモノは少なかったので、その都度、新しいモノを創造しなければなりません。当然、仕事では失敗も多かったですし、毎日が朝から晩までの激務。しかし私の先輩たちは、「こういうモノをつくりたい」という信念に満ちており、私自身も仕事の達成感に魅せられていました。ですから、そうした環境をつらいと思ったことは一度もありません。後に工場長、本社のエンジニアリング部長になった時も、自分がやるべきことははっきり見えていましたし、自分がやりたいことも明確にわかるようになりました。さらに酪農、物流、そして研究所を見てきた経験が、後に私が社長になったときに生きることになったのです。
社員全員の合意形成で、100年後を目指す
2012年、当社の社長に就任した私は、「社長としてやらなければいけないこと」「社長じゃなければ、できないこと」に悩みました。そしてたどり着いた答えは、社員の意識改革にあると確信しました。良い商品さえつくれば、高くてもお客さまに買っていただけた時代もあったかもしれません。しかし現代は、こちらからお客さまが求めているものを知り、創造していく必要があります。そして積み上げてきた研究データや知見を、お客さまのニーズに合わせ、新しい商品をつくっていかなければいけないのです。もちろんそのためには、社員全員が合意形成を図る必要があるでしょう。
その中で組織のリーダーとしての役割は、私が少年時代にすでに経験していることでもあります。それはいわば、小学生の頃の学級委員と同じ。みんなを引っ張るが、自分だけが突っ走っても駄目だという気持ちです。そうやって私は、当社を次の100年へと伝えるつもりなのです。若いみなさん方も、自分の経験や蓄積を未来に生かすつもりで生きてもらいたい。
Loading...